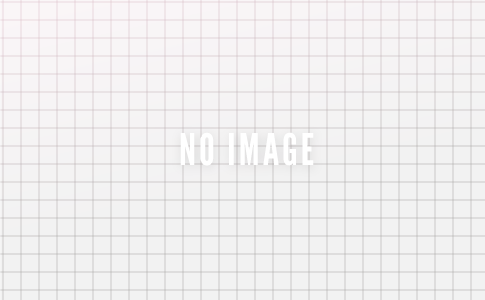今朝は朝6時に起きました。窓を開けると、夜が明けるのが日に日に早くなっているのを感じます。冬が終わってそろそろ春が来るのだな、と思う時期になりました。
今週金曜日は立春です。二十四節気では立春を過ぎると春です。また、新しい一年の始まりの日でもあります。年が改まった際、新年の抱負を決めることが多いですよね。私の友人は「お正月の1月1日よりは、立春2月4日に決める。」と言っていました。
これを聞いた時に、立春に新年の抱負を決めるのはいい考えだと思いました。太陽に長く照らされると、ポジティブな気持ちになりますよね。夜が明けるのが早くなってきて、昼間の太陽の光の暖かさを感じると、この一年が充実させようと、やる気が出てきます。今年は、一月に「今年やりたいこと」を決めましたが、来年からは、立春にしてみようかな。
そんな2月のお稽古で使ってみたい茶杓の銘、季語を紹介します。
- 寒松(かんしょう)
- 春告鳥(はるつげどり)
- 暁(あかつき)
- 東風(こち)
- 飛梅(とびうめ)
- 遠山(とおやま)
- 柳の糸(やなぎのいと)
↓こちらにも上記以外の二月の季語を紹介しています
寒松(かんしょう)
冬の寒さに耐える松。また、寒松千丈(かんしょうせんじょう)は四字熟語で、松は寒い冬でも変わらぬ緑を保つことから、義を守るという意味にもなる
春告鳥(はるつげどり)
うぐいすの異名。他の鳥よりも早く鳴き始め、春になったことを知らせることから
暁(あかつき)
夜から朝になる明け方。一日の始まりの夜明けと、一年の始まりの夜明けもあります。
東風(こち)
春になると吹く東からの風
飛梅(とびうめ)
下記言い伝えにある、太宰府天満宮に植えられている梅の木の名前です。
菅原道真が大宰府(だざいふ)に左遷されるとき、大切にしていた庭の梅の木に「東風(こち)吹かば匂ひおこせよ梅の花あるじなしとて春を忘るな」の一首をかけて去ったところ、その梅の木が道真を慕って、大宰府にまで飛んで行ったという故事。また、その故事にちなんだ、太宰府市安楽寺の梅。
weblioから引用
遠山(とおやま)
遠くの山。なぜ遠くの山が2月の茶杓の名なのか、気になるところです。私なりに、考えると、太陽の光の角度が高くなってきて、遠くの山も美しく見える時期ということなのでしょうか。
柳の糸(やなぎのいと)
糸のように細い柳の枝。まだこの時期には、芽も小さいので、枝は細く見えるのでしょう。もう少し新芽が育ってくると「芽吹き柳」となります。
そのほかの季語
残雪(ざんせつ)
雪解(ゆきどけ)
淡雪(あわゆき)
早春(そうしゅん)
雪間(ゆきま)
初午(はつうま)
下萌(したもえ)
鶯笛(うぐいすぶえ/おうてき)
春寒(しゅんかん)
薄氷(うすごおり)
紅梅(こうばい)
梅日和(うめびより)
槍梅(やりうめ)
梅が香(うめがか)
白梅(はくばい)
梅月(ばいげつ)
初音(はつね)
芽吹柳(めぶきやなぎ)
啓蟄(けいちつ)
柳色(りゅうしょく)
季語をみているだけでも、暖かくなってくる気配を感じますね。お稽古でこれらの銘を使いたいです。